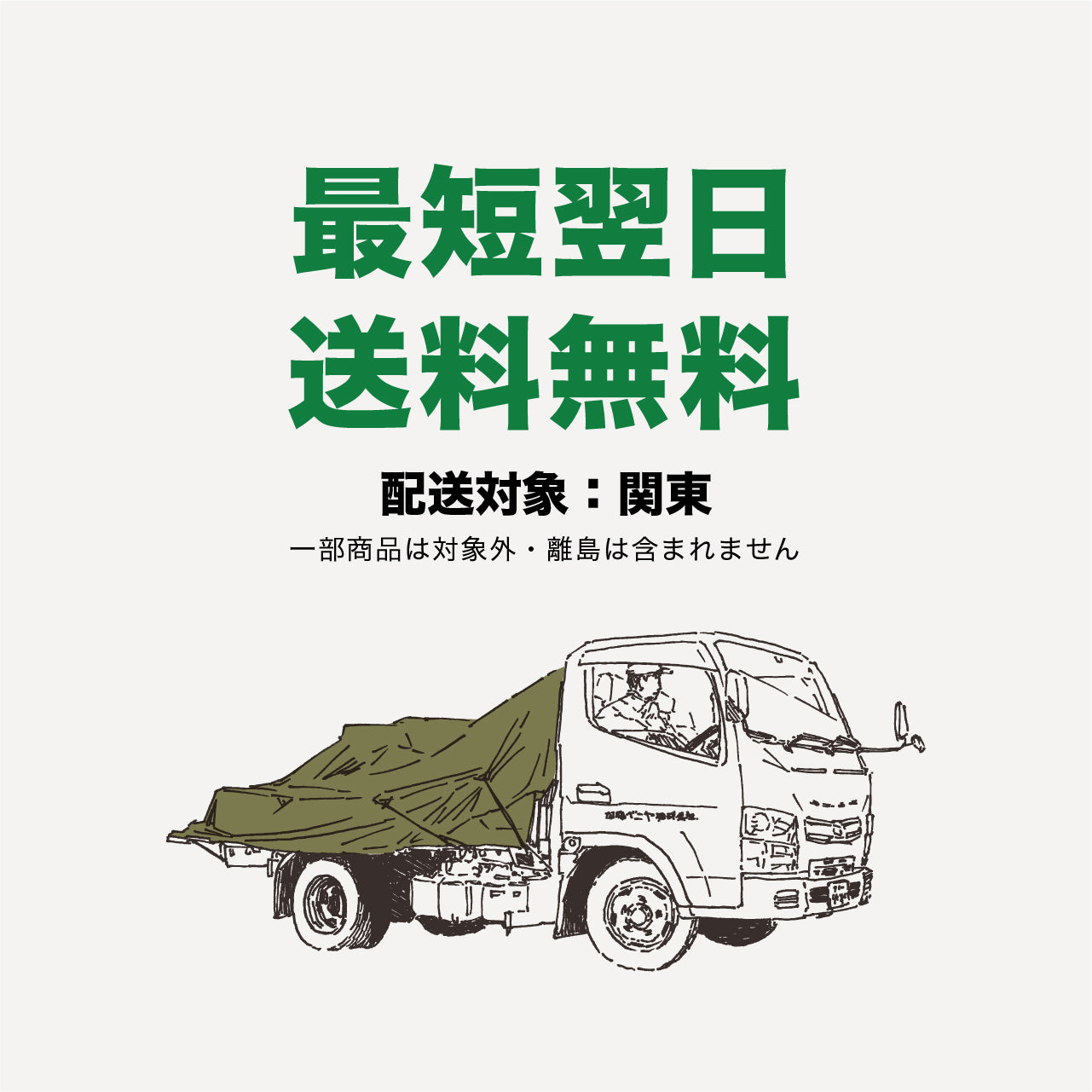戸建て建築の現場で、合板は本当に文字通り、家を支える「基盤」となる材料です。壁に床に屋根に、その存在感は大きいですよね。
そして、現場で合板を扱っている皆さんなら、おそらく毎日目にしているであろう、あの見慣れたサイズがあります。
910mm × 1820mm
いわゆる「サブロク板(3×6板)」と呼ばれるサイズです。ほとんどの合板が、このサイズを基本として製造・流通しています。
「なんで合板って、どれもこのサイズなんだろう?」
もしかしたら、一度くらいはそんな風に思われたことがあるかもしれません。僕も当たり前すぎて、改めて考えることはほとんどありませんでした…。実はこのサイズには、日本の建築の長い歴史と、現場での都合がぎゅっと詰まっていたんです。
今日は、この「サブロク板」のサイズに隠された理由を、皆さんと一緒に探ってみたいと思います。普段何気なく使っている材料の、ちょっとした秘密を知ることで、また違った面白さが見えてくるかもしれません。
サブロク板のルーツは、日本の「尺貫法」にあり
結論から言うと、合板の910mm×1820mmというサイズは、日本の伝統的な長さの単位である「尺貫法」(しゃっかんほう)に基づいています。
具体的には、
- 910mm = 約3尺(909.1mm)
- 1820mm = 約6尺(1818.2mm)
なんです。
そう、「3尺×6尺」だから「サブロク板」なんですね。メートル法が主流になった現代でも、建築の分野ではこの尺貫法、特に「1間(いっけん)=6尺=約1820mm」、「半間(はんげん)=3尺=約910mm」といった単位が、建物のモジュールとして根強く残っています。
畳のサイズも、この尺貫法が基になっています。一般的な江戸間の畳は、約880mm×1760mmですが、これは柱の内々寸法である910mm×1820mmの中に納まるようにできているんですね。
つまり、合板のサブロクサイズは、古くから日本の建築で基準とされてきた「間」という単位に合わせて作られている、ということなんです。

このサイズが現場にもたらす利点
建物の設計が、今でもこの尺貫法のモジュール(910mmグリッドなど)を基に行われることが多いのは、合板のサブロクサイズにとっても大きな利点になります。
主なメリットとしては、以下のような点が挙げられるのではないでしょうか。
- 現場での割付がしやすい: 建物の柱間隔や壁の長さに合わせて、無駄なく効率的に合板を配置しやすいんです。カットする回数を減らしたり、端材を少なくしたりすることに繋がります。
- 運搬や搬入が比較的容易: 910mm×1820mmというサイズは、大人が複数人で運ぶ際に、比較的取り回しがしやすいサイズだと言えます。大きすぎず、重すぎず(もちろん厚みにもよりますが)。トラックへの積載や、現場の通路を通す際にも、このサイズ感が基準になっていることが多いのではないでしょうか。
- 国内での標準化: 長い間、このサイズが標準として使われてきたため、製造や流通のシステムが確立しています。安定した供給や、コストにも良い影響を与えている側面があるかもしれません。
このサイズゆえの、現場の「モヤモヤ」も?
尺貫法に基づいたサブロクサイズは、日本の建築に最適化されてきたサイズと言えます。しかし、現場では「サブロク板だからこそ、ちょっと困るんだよな…」というモヤモヤもあるかもしれません。
例えば、次のような経験はありませんか?
- 狭い通路や階段での搬入: 現場の状況によっては、廊下や階段を回すのが一苦労、なんてこともありますよね。養生した壁にぶつけないように、慎重に、慎重に…という場面。
- エレベーターに入らない!: 都心部の狭小地など、エレベーターで資材を運ぶ現場では、サブロク板が入らず、結局階段で手運び…なんて経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。
- 細かいカットや端材: 基準のモジュールから外れる部分や、開口部の周りなど、どうしても細かいカットや、使いきれない端材が出てしまうのは避けられません。
これらの苦労も、このサブロクという「当たり前」があるからこそ生まれるもの。現場のプロの皆さんは、こうしたサイズにまつわる苦労も、長年の経験と知恵で乗り越えているのか…としみじみとしてしまいます。養生をしっかり行う、端材を有効活用する、現場を常に整えておくなど、様々な工夫があるはずです。
サブロクだけじゃない! 現代の現場と合板サイズ
最近では、ツーバイフォー(2×4)工法のように、インチ・フィートを基にしたモジュール(約303mmや約406mmグリッド)で建てられる住宅も増えています。そうした現場では、サブロクサイズだけでなく…
・メーター板(1000mm×2000mmなど/メーターモジュールに合わせた寸法)
・サンパチ板(910mm×2420mm)
・シハチ板(1210mm×2420mm)
などが使われることもあります。
大きな合板を使う利点は、壁や床の途中で継ぎ目が出にくく、耐力壁の強度を確保しやすい点など。
しかし、その分、重くて運ぶのが大変だったり、現場での取り回しに工夫が必要だったりします。
それぞれのサイズに、使われる工法や現場の状況に合わせた理由やメリット・デメリットがあるんですね。
まとめ
普段、何気なく使っている合板の910mm×1820mmというサイズ。
その背景には、日本の伝統的な建築モジュールである尺貫法があり、長い年月をかけて日本の住まいづくりに合わせて最適化されてきた歴史がありました。
このサイズがあるからこそ、現場での割付がしやすかったり、運搬が比較的容易だったりする利点がある一方、
現場の状況によっては搬入に苦労したり、端材が出てしまったりといった側面もあります。
私たちは建材屋として、様々なサイズの建材を現場の皆さんにお届けしていますが、その裏側にあるプロの皆さんの運搬や施工の苦労、そしてそれを乗り越える知恵や工夫を、改めて感じています。
サイズを知ることは、材料への理解を深め、現場での効率や無駄を減らすヒントにもなるかもしれません。皆さんの日々の作業の一助となれば嬉しいです。